財布の中に当たり前のように入っている硬貨。
1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉。
これらは「日常の支払い手段」として使われていますが、実は硬貨には「作るためのコスト(製造原価)」があり、その金額は年々上昇しています。
特に金属価格の高騰やエネルギー費用の上昇により、一部の硬貨は「原価が額面を上回る」状態、つまり“作るだけで赤字”という逆転現象が起きています。
本記事では、硬貨の原価がどれほどかかるのか、そしてなぜそんな事態になっているのかを、経済的な観点から詳しく解説します。
1. 硬貨はどこで作られているのか
日本の硬貨は「造幣局(ぞうへいきょく)」で製造されています。
造幣局は財務省の管轄で、大阪本局を中心に、広島やさいたまの支局でも硬貨が作られています。
製造された硬貨は日本銀行に納入され、そこから市中の金融機関を通して流通します。
造幣局の業務報告書によると、硬貨の製造には以下のようなコストがかかっています。
-
金属素材(銅、亜鉛、ニッケル、アルミニウムなど)
-
電力・燃料費(溶解・圧延・刻印などの工程)
-
人件費・設備維持費
-
検査・包装・輸送費
つまり、単に「金属を溶かして型を打つ」だけではなく、工業製品としてのコストが積み重なっています。
2. 各硬貨の原価はどれくらい?
造幣局が公表する詳細な製造コストは非公開ですが、財務省や国会答弁などの資料を基に推定値が知られています。
以下は近年の代表的な硬貨の原価傾向です(推定値)。
-
1円玉(アルミ製):約3円〜5円
-
5円玉(黄銅製):約7円前後
-
10円玉(青銅製):約9円前後
-
50円玉(白銅製):約15円前後
-
100円玉(白銅製):約20円前後
-
500円玉(ニッケル黄銅またはバイカラークラッド):約30円〜40円
この数字を見ればわかる通り、1円玉は1円の価値しかないのに、作るのに3円以上かかるという不合理な状態です。
つまり、国家が1円玉を製造するたびに、約2円以上の損失を出しているということになります。
3. なぜ原価が上がっているのか
硬貨の製造原価が上昇している背景には、主に以下の3つの要因があります。
(1)金属価格の高騰
硬貨に使われる金属はすべて国際市場で取引されています。
特に銅、ニッケル、亜鉛といった素材は、電気自動車・電子機器・インフラ建設などの需要増で価格が上昇。
たとえば銅は2000年代初頭に1トン約2,000ドルだったのが、近年では約8,000ドルを超えることもあります。
この原材料高が、硬貨製造コストに直結しています。
(2)エネルギー・人件費の上昇
金属を溶かして圧延し、打刻するには大量の電力と燃料が必要です。
また、造幣局の設備更新や人件費も年々上がっています。
これらの固定費も、硬貨1枚あたりの原価を押し上げる要因となっています。
(3)キャッシュレス化による製造数減
現金の利用が減ることで、製造枚数が少なくなり、スケールメリットが失われます。
大量生産によって単価を抑えていた時代に比べ、現在は少量多品種の生産となり、1枚あたりのコストが上がっているのです。
4. 「作れば赤字」でも硬貨を作る理由
では、なぜ日本政府は赤字を出してまで硬貨を作り続けているのでしょうか。
理由のひとつは「通貨としての信頼性」です。
日本円は、硬貨と紙幣が揃って初めて通貨体系として成立しています。
少額決済や自動販売機、駐車場料金など、日常生活において硬貨は依然として不可欠です。
また、造幣局は硬貨以外にも勲章やメダルなどを製造しており、その技術の維持にも硬貨製造が貢献しています。
つまり、硬貨の製造は「国家の象徴」としての意味合いもあるのです。
5. 他国の硬貨原価との比較
日本だけでなく、アメリカやヨーロッパでも同様の問題が起きています。
たとえば米国では、2023年時点で以下のようなコストが報告されています。
-
1セント硬貨(ペニー):1枚あたり約2.7セント
-
5セント硬貨(ニッケル):1枚あたり約10セント
つまり、アメリカでも最小単位の硬貨を作るだけで赤字が発生しています。
このため、カナダやオーストラリアではすでに1セント硬貨を廃止しており、日本でも将来的に同様の議論が起こる可能性があります。
6. 日本でも「1円玉廃止」の議論が進む?
キャッシュレス決済の普及により、1円単位の支払い機会は確実に減少しています。
また、電子マネーやQRコード決済では「小数点以下を四捨五入する」処理が一般化しており、現金の端数処理がなくても支障がない仕組みが整いつつあります。
一方で、公共料金や税金、切手、郵便料金など、まだ1円単位で設定されている価格も多く、すぐに廃止することは難しいのが現状です。
ただし、硬貨の原価が額面を上回る状況が続けば、財政的な観点から見直しは避けられないでしょう。
7. 硬貨の原価と税金の関係
硬貨は「政府貨幣」として、財務省が直接発行します。
紙幣(日銀券)は日本銀行が発行しますが、硬貨の発行益(いわゆる鋳造益)は政府の収入として「国庫」に入ります。
しかし、原価が額面より高ければ鋳造益はマイナス、つまり赤字となります。
これを補うのは最終的に国民の税金であり、極端に言えば「1円玉を作るために税金を使っている」構造になっています。
8. 今後の展望:デジタル円と硬貨の行方
日本銀行は「デジタル円(CBDC)」の実証実験を進めています。
これが導入されれば、少額決済も電子的に完結し、硬貨の需要はさらに減少するでしょう。
ただし、災害時や停電時など、現金が唯一の支払い手段となる場面も存在します。
したがって、完全な硬貨廃止ではなく、「流通量の削減」「製造効率化」「再利用の促進」が現実的な対応になると考えられます。
まとめ:1円の価値を見直す時代へ
硬貨は単なる支払い手段ではなく、「通貨の信頼」を象徴する国家インフラの一部です。
しかし、金属価格やエネルギーコストの上昇により、硬貨を作るたびに財政負担が増しているのも事実です。
私たちが1円を大切に扱うこと、そしてキャッシュレス時代における「通貨の形」を考えることは、経済全体を見つめ直すきっかけになります。
1円玉の裏には、国家財政・資源・技術、そして“お金の意味”そのものが詰まっているのです。
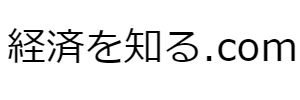
Leave a comment