日本では「金融資産(預貯金+株式・投資信託など)」をどれくらい持っているのか、特に年齢別の中央値がどれほどかという疑問を持つ人が多いでしょう。
平均値だけでは資産格差の実態が見えにくいため、中央値(中央値とは、資産を少ない順に並べたときに真ん中になる値)が重要です。
本記事では、最新の調査データをもとに、日本人の年齢別金融資産の中央値がどれくらいか、どのような傾向があるか、また格差要因と対策について詳しく解説します。
金融資産中央値とは何か?平均値との違い
まず前提として、「金融資産」と「中央値」が何を意味するかを押さえておきましょう。
-
金融資産とは、預貯金だけでなく、株式・投資信託・金銭信託・債券・保険商品など“流動性または比較的換金性のある資産”を含むものを指す調査が多いです。
-
中央値とは、調査対象を資産額の少ない順に並べたとき、ちょうど中央に位置する値。極端に資産が大きい人(上位)やほぼ資産を持たない人(下位)の影響が平均値ほど出ないため、実態を反映しやすい指標です。
平均値では資産を非常に多く持つごく少数の人が数字を押し上げることがあり、「多くの人がそれに近い資産を持っている」という誤解を生むことがあります。それに対して中央値は“典型的な”人の実態に近い数値を示します。
最新データ:日本の年齢別金融資産の中央値(貯蓄ベース含む)
以下は信頼できる機関・調査による、年代別の金融資産(あるいは貯蓄含む)中央値に関するデータです。このデータをもとに、各世代がどのくらいの資産を持っているか、傾向を読み取ります。
主な調査と数値
-
ソニー生命「年月別貯蓄中央値」
金融資産を保有している世帯に限定した年代別中央値は、20代で約120万円、30代で約315万円、40代で約500万円、50代で約700万円、60代で約1,200万円、70代で約1,100万円というデータがあります。
ただし、金融資産を保有していない世帯も含めた中央値になると、20代で10万円、30代で130万円、40代で180万円、50代で200万円、60代で530万円、70代で650万円とかなり低くなります。 -
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」令和3年調査(二人以上世帯・単身世帯)
この調査では、二人以上世帯の年齢別貯蓄額の中央値が以下のようになっています(年代順に若い→高齢):20代で約63万円、30代で約238万円、40代で約300万円、50代で約400万円、60代で約810万円、70代以上で約1000万円。
単身世帯では20代で約20万円、30代で約56万円、40代で約92万円、50代で約130万円、60代で約460万円、70代以上で約800万円というデータがあります。 -
他の金融資産含む調査例
“みんなの貯金はどのくらい?”という調査では、2人以上世帯で20代の中央値が185万円、30代が360万円、40代が520万円、50代が700万円というデータがあります。 -
総務省統計・貯蓄・負債編など世帯全体のデータ
たとえば、「二人以上の世帯勤労者世帯」の貯蓄を保有している世帯(貯蓄ゼロ世帯を除く)での中央値は、最近のデータで約947万円。
年齢別中央値の傾向と特徴
これらのデータから、年齢別金融資産の中央値には以下のような傾向と特徴が読み取れます。
-
若年世代(20代)
20代では中央値が比較的低く、多くの人が100万円未満または数十万円程度の資産しか持っていないことが普通です。単身世帯では20万円前後、二人以上世帯でも60~70万円程度というデータがあります。 -
30代~40代
この世代になると、結婚・子育て・住宅取得などライフイベントが増える一方で収入も上昇するため、中央値が一気に上がります。30代で約200~300万円、40代で約300~500万円というのが多くの調査で共通する範囲です。 -
50代
50代では資産形成のピーク期近くとなるため、中央値が更に高まります。二人以上世帯で400~700万円程度。貯蓄保有世帯に限るデータではもっと高い中央値が報告されています(たとえば700万円以上)。 -
60代以上
60代以降になると、仕事をリタイアしたり、退職金を得たり、資産を溜める期間が長いことなどにより中央値が大きく上昇します。特に貯蓄保有世帯では800万円~1000万円を超えることが一般的なラインとも言えます。 -
世帯構成の影響(単身/二人以上)
単身世帯の中央値は二人以上の世帯と比べてかなり低く、同じ年齢でも資産の中央値が異なることが明らかです。理由としては収入の違いや生活コスト、共有できる支出の分散などが考えられます。 -
金融資産を持たない世帯を含むかどうかの差
金融資産を全く持っていない世帯を含めると中央値は大きく下がります。資産を持っていない人が一定割合存在するためです。貯蓄保有世帯での中央値と、保有世帯以外も含めた中央値との差が、実態の格差を示しています。
データ間の差異と注意点
中央値データを見比べる際には以下の点に注意が必要です。
-
調査対象の定義:金融資産に何を含めるか(預貯金のみ、株式や投信含むか、負債を引くかなど)が異なる。これによって数値が上下する。
-
世帯構成:単身か二人以上か(家族世帯か)によって生活コスト・収入源が異なるため資産保有状況が大きく異なる。
-
保有世帯のみか全世帯か:資産ゼロ世帯を含めると中央値は下がる。多くの調査でこの違いが大きい。
-
調査時期:インフレ・株価・不動産価格・利子率などの影響で毎年変動がある。最新データを使うことが重要。
-
地域格差・所得格差:都市部と地方、職業・所得階層による差が大きく、中央値だけでは「平均的な人」がどのくらいかを把握するにあたり限界がある。
なぜ中央値は低めに見えるのか:格差の要因
中央値が思ったより低いと感じる人が多いと思いますが、これは複数の理由によります。
-
所得が低めの人、若年層、非正規雇用・パート・アルバイトなどの比率が上がっている世帯が多いため。
-
支出が大きいライフイベント(教育費・住宅ローン・子育て等)を抱えている時期が30代~40代であり、貯蓄に回せる余裕が少ない。
-
貯蓄ではなく消費や借金返済優先の世帯も少なくない。住宅ローン・車のローン・教育ローンなど負債が資産を相殺するケースもある。
-
投資に回している資産があっても評価額を含めていない調査や、流動性が低い資産(不動産など)を含まない調査もあり、“見えていない資産”がある。
-
資産を持っていない世帯(ゼロ資産世帯)の存在が中央値を押し下げる。特に若年世代でその割合が高い。
世代別中央値を引き上げるためのヒント・実践策
年齢別中央値が低いという事実を踏まえて、個人・社会両面で資産を増やすための具体的なヒントを紹介します。
-
若いうちからの貯蓄習慣の確立
収入が少なくても、毎月一定額を貯金または投資に回すことで資産の累積が可能です。複利の効果を活かすため、若年期からのスタートが重要です。 -
支出の見直しとライフイベントの計画
住宅購入・子育て・教育費など大きな支出を見越して予算を立て、無駄な支出を抑えること。ローンの条件・借入先を比較するなどの工夫も効果的です。 -
金融資産の分散と投資活用
預貯金だけでなく、リスクを取れる部分は株式・投資信託などを含めることで資産の成長が期待できます。ただし、リスク管理は慎重に。 -
負債管理をしっかり行う
借入金利の高い負債を先に返す、ローンの見直しをするなどで、資産増加を妨げる要因を減らす。 -
税制・社会制度の活用
確定拠出年金(iDeCoなど)、NISAなど税制優遇制度を使うことで、手取り収入を効率的に資産へ換えることが可能です。 -
長期的視点での資産形成
短期のショック(株価変動・金利変動など)に左右されず、長期にわたってコツコツと資産形成を続けることが成功には不可欠です。
中央値だけでは語れないこと:限界と今後の注目点
中央値は実態を把握するのに有用ですが、それだけでは見えない要素も多いです。今後注目すべき視点を挙げます。
-
上位層の資産集中
資産のトップ層がどれほど資産を持っているかが平均値を大きく引き上げており、格差の度合いを測るにはパーセンタイル(例えば上位10%など)のデータが必要。 -
負債を差し引いた純資産
住宅ローンなどの借入が残っている場合、金融資産だけで豊かさを評価すると偏る可能性があります。 -
地域・都市 vs 地方の差
東京など都市圏では収入・資産の水準が高いが、地方では少ないというケースが多く、全国ベースの中央値が地域差で見えにくい。 -
インフレ・物価上昇の影響
預貯金の実質価値はインフレで減ることがあります。名目値だけでなく実質価値を考えることも重要です。 -
世代ごとの価値観の変化
若年世代で貯蓄より経験や消費を重視する人が増えている、投資リスクの受容度が異なる、などの文化・価値観の違いも資産保有に影響します。
まとめ
日本の年齢別金融資産中央値をもとに見えてくることは、「資産を十分に持っている」という人は決して多くない一方で、年齢が上がるほど中央値が上昇するという典型的な資産形成の傾向が明確であることです。若年世代では数十万円〜数百万円程度が中央値になることが多く、30代~50代で数百万円から700万円前後、60代以降で800万円~1000万円超えが中央値の一つの目安となります。
ただし、中央値だけで十分な将来設計ができるわけではなく、支出や負債、資産を持たない世帯の割合なども考慮する必要があります。これらを踏まえて、自分自身の資産状況を把握し、将来へ向けた資産形成を意識することが大切です。
金融資産の中央値は、平均値よりも「多くの人の実態」に近く、将来設計やマネープランを考える際の参考指標として非常に有効です。年齢別データを活用し、自分がどの位置にいるかを把握し、必要な対策を早めに始めることで、より安心な経済生活を築くことが可能です。
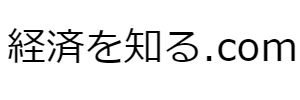
Leave a comment